地域物流の効果検証(普及に向けた調査)
前回は、共同輸配送(地域物流)の効果について解説しました。
- ・低迷が続く積載率の向上(効果:重量換算で4,573kg増、34.7ポイント改善)
- ・幹線輸送ドライバーの拘束時間を抑制(効果:-1時間53分抑制、18.2ポイント改善)
考察として、物流課題を解決できる可能性があることにも言及しました。
- ・リソース(車両、ドライバー)の適正化により、トラック輸送の需給ギャップを解消
- ・労働環境の改善により、ドライバー不足を解消
※詳細は、第4話を参照ください。
これらを実現するためには、より多くの企業に受け入れられる必要があります。
そこで今回は、共同輸配送の普及の可能性について解説します。
- ・検証したプロトタイプがより多くの企業に受け入れられるか
- ・共同輸配送のニーズはあるか
検証した運用(プロトタイプ)
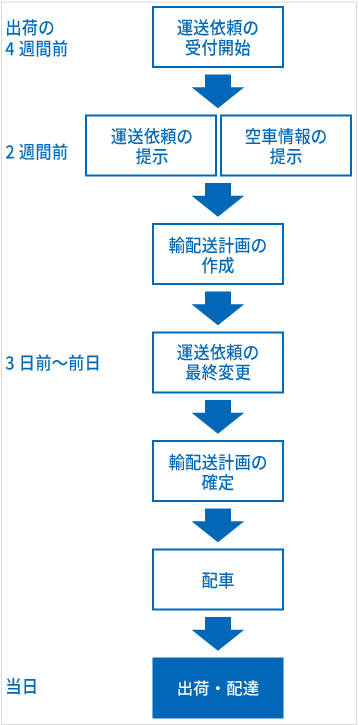
検証に参画した主なメンバー
- ・荷送人企業:岐阜県内の企業2社(A社、B社)
荷物は実際の受注から検証に適したものを選定、提供いただいた - ・運送事業者:3社
集荷、幹線、配達の3区間に分け、それぞれ担当企業を決めて輸送 - ・サービスプロバイダ:当社
荷送人企業からの運送依頼と、運送事業者からの空車情報とをマッチング
運用フローとスケジュール
輸配送だけでなく、出荷スケジュールの調整や配車など、一連の運用を全て行いました。
- ・出荷の4週間前
運送依頼の受付を開始
荷送人企業からサービスプロバイダへ、希望出荷期間を付けた依頼情報を提示 - ・出荷の2週間前
- - 荷送人企業:依頼情報を決定
- - 運送事業者:空車情報を提示(提供可能日、車種など)
- - サービスプロバイダ:輸配送計画(第1段)を作成し、運送事業者へ提示
- ・3日前~前日
- - 荷送人企業:受注に変更が生じた場合のみ、運送依頼を変更して確定
- - サービスプロバイダ:輸配送計画を確定させ、運送事業者へ提示
- - 運送事業者:輸配送計画に沿って配車し、結果をサービスプロバイダへ提示
- ・当日
輸配送計画に基づき、出荷・配達を実行
このプロトタイプは普及できるか
検証では問題なく運用できましたが、他の企業でも受け入れてもらえるでしょうか。
そこで、当社メールマガジン会員へアンケート調査を行いました。
先の通り、荷送人企業による運送依頼の提示には受注情報が必要です。そして、その受注情報の精度が高ければ高いほど、正確な運送依頼の提示ができるため、特に「受注予定情報」に関する設問を注視しました。
以下は、荷送人企業の立場での回答結果です。
受注予定情報は物流シーンで活用可能か
予定情報は存在するか、活用しているか
- ・「予定情報がある」と回答した企業が45%
- ・活用方法:全ての企業が「生産または調達計画に活用」と回答
- ・活用ニーズ:「物流でも予定情報を活用したい」との回答が40%
いつ、どのように予定情報を取得するか
- ・取得タイミング:「出荷日の1か月以上前」が83%、「2週間前まで」が100%
- ・EDI化率:「20%以下」が75%
多くの企業が予定情報を取得しており、取得タイミングも当プロトタイプと合致しているため、おおむね問題ありませんでした。ただし現在のEDI化率は低いため、簡単かつ安全に情報共有ができる仕組みが必要と考えられます。
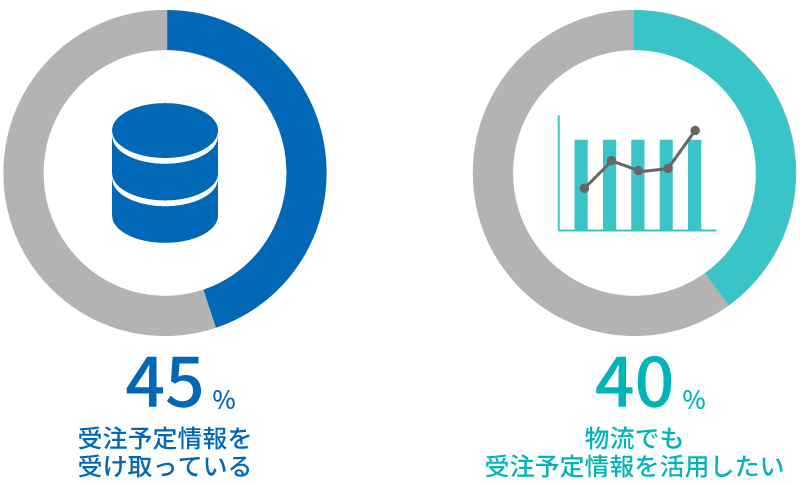
運用フローに無理はないか
プロトタイプのフローを実際に運用できるか、検証結果をもとに考察します。
受注情報(予定情報、確定情報)の活用
変更の都度、人手による輸配送計画の修正は困難と捉え、情報システムやAIなどを活用した運用検討が必要
また、早期割引(※1)と調整協力割引(※2)など、荷主企業へのインセンティブの組み込みも重要
※1 早期割引:
運送依頼を確定したタイミングが出荷日の2日以上前の運送依頼に対し適用する割引
※2 調整協力割引:
早期割引:出荷日・納品日に2日間以上の猶予期間を設けた運送依頼に対し適用する割引
第2話で簡単にご紹介していますが、ご関心のある方は以下協議会までお問い合わせください。
空車情報の活用
- ・情報の内容については、おおむね問題なし
- ・検証では車両単位でリソースを確保したが、今後リソースの一部(空きスペース、空き時間)のみでも登録可能にする想定であるため、車種ではなく「積載可能量」を用いて計画するよう運用変更が必要
共同輸配送のニーズはあるか
ここまで運用上の検証をしてきましたが、そもそも共同輸配送のニーズはあるのでしょうか。
同じく当社メールマガジン会員にアンケート調査を行った結果、「利用したい・条件によって利用したい」との回答は61%でした。
「業界の壁を越えた共同輸配送」の構築・普及を目指すとした協議会へも多くの企業が参画しており、その点からもニーズがあることがうかがい知れます。
ただし、荷主企業へのインセンティブが条件になると考えており、早期割引や調整協力割引の実現を含め検証を重ねています。
検証で認識した課題の解決に向けて
検証ではニーズを確認できたほか、プロトタイプの課題点を洗い出すことができました。
2020年7月の検証以降は、課題解決に向けた活動を行っています。
- ・プロトタイプの高度化:システム・運用の両面からの見直し
- ・社会実証(試験運用)の実施:当検証より規模を大幅に拡大、荷主企業57社が参画
また、現在は「SIP地域物流ネットワーク化推進協議会」においてワーキンググループを発足、共同輸配送の研究を含めた物流クライシスを乗り越えるためのワーキングを開始しました。
この取り組みでは、会員間の活発な意見交換が行われます。物流クライシスや持続可能な物流体制についてご関心のある方は、ぜひご参加ください。
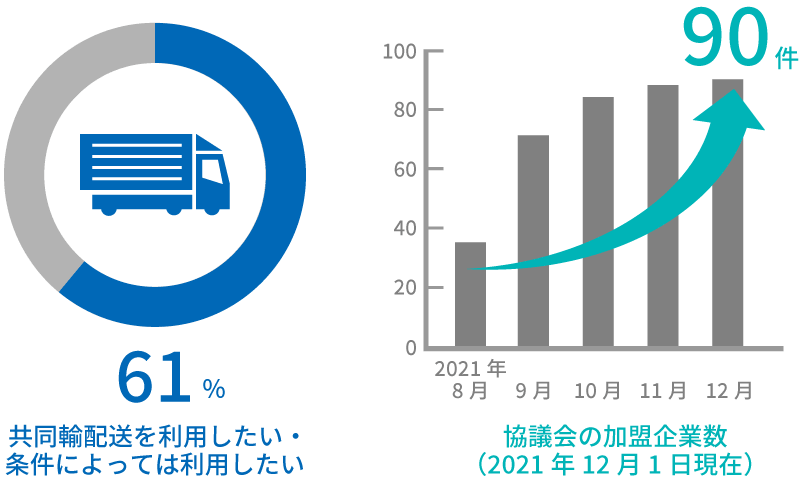
まとめ
今回の検証では、以下の2点が確認できました。
- ・「業界の壁を越えた共同輸配送」は十分なニーズがある
- ・運用に関しては、プロトタイプを改良することで実務にも対応可能である
また、プロトタイプの課題点を洗い出すこともできました。
それらを解決するために、プロトタイプの高度化や、荷主企業57社が参画しての社会実証(試験運用)を実施しました。
今後、この共同輸配送のように情報を活用し物流を最適化する動きは活発化するでしょう。
最新の 総合物流大綱(2021年度~2025年度版)では「物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化」が方針の1つとして掲げられており、「サプライチェーン上の様々なデータを蓄積・共有・活用し、物流を効率化」するための施策がSIP「スマート物流サービス」プロジェクトを中心に社会実装される予定です。
時代の波に乗って、これらスマート物流サービスをうまく活用し、輸送力の安定確保と自社物流の効率化を進めましょう。
- ■ SIP地域物流ネットワーク化推進協議会では、会員を募集しています。
- ・入会資格 本協議会の目的・活動内容にご賛同の企業・団体・個人
- ・年会費 2022年度は無料
・入会のお申込みはこちらから








