新WMS稼働日を安心して迎えるためのチェックポイント
WMS(倉庫管理システム)の導入・リプレースプロジェクトにおいて、導入前に行う準備作業は非常に重要です。 導入準備を入念に行っておくことで、立ち上がり時のトラブルを低減します。 しかしどれだけ入念に準備を行っても、「トラブル無く稼働するか」「十分検討したつもりだが、本当に問題ない仕様になっているか」など、新WMSが運用に耐え得るか不安を感じる方も多いのではないでしょうか。 そこで当コラムでは、安心して本番を迎えるためにすべきことを解説します。 受け入れテストで仕様に抜け漏れが無いかを確認する方法や、新WMSを稼働させる準備は整ったかを確認するチェックリストなど、具体的な情報をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
導入準備の目的や全体の流れ、導入計画の立案については、別コラム「WMSの導入は事前準備が成功のポイント」で紹介しています。
目次
コラムのポイント
- ・新WMSのテスト~稼働日当日までの流れと行うべきことを解説
- ・システムの仕様に抜け漏れを確認する方法など、安心して稼働日を迎えるためのポイントを紹介
- ・チェックリストなどのサンプルを掲載
導入準備(実行編)
受け入れテスト
新WMSが仕様(設計書)通りか、運用に耐え得るかをユーザー企業がチェックします。 この工程では、起こりうるあらゆるパターンを洗い出してテストシナリオを作成し、実際にデータ入力したり帳票を印刷してテストします。帳票やロケーションに表示のバーコードも、可能な限り全種類のスキャンをしておきます。
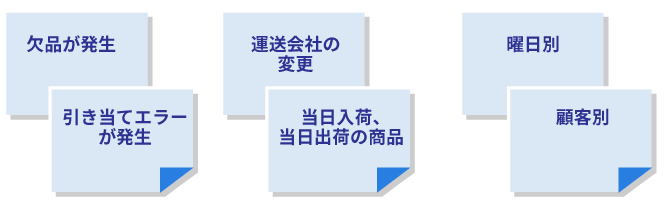
この工程は、導入計画の立案と同じくらい重要です。 運用リハーサルに充分な時間が取れそうにない場合は、特に入念に行いましょう。
マニュアル作成
以下2種類のマニュアルを作成します。
- ・システムの操作マニュアル ベンダーが作成し、リーダー教育で使用
- ・業務マニュアル ユーザー企業で作成 要件定義で合意した業務フローやシステム操作マニュアルをベースにすると作りやすい
リーダー教育
入荷・出荷など業務ごとのチームリーダーや、事務所のリーダーを対象として操作説明会を行います。 講師は主にWMSベンダーが担当し、運用が関わる質問には物流部門が回答することでスムーズに進行します。 また、担当する商品や顧客ごとに運用が異なる場合は、説明会で個別運用をどこまで・どのように説明するのかをあらかじめ検討しておきましょう。作業員への教育は別途期間を設け、各リーダーが講師役となり実施します。
運用リハーサル
現場で実データを使用し実際に動かせてみて、漏れなく導入準備が完了しているかチェックします。 主な目的は、4つです。
- ・現場教育(トラブルがあっても現場で判断し対応できる状態になるとベスト)
- ・実際の運用に即した環境(データ、場所、機器台数など)でのレスポンスを確認する
- ・導入計画、マニュアルの問題点を洗い出す
- ・運用上の問題点を洗い出し、その対策も取り決めておく
また、運用リハーサルは、次の工程「切替判断」を行うために必要な情報を取得する場でもあります。 事前にチェックシートを作成し、確認漏れがないようにしましょう。

切替判断
運用リハーサルの結果をもって、新WMSへ切り替えてよいかを判断します。 いつ、何がどうなれば切り替えて良いのか、誰が判断するのか、など事前に判断基準を明確にしておくことが重要です。その基準を確認するためにチェックシートを作成しておき、運用リハーサルで確認します。 また切り替えは、物流業務だけでなく連携する基幹システム、ひいては売上にも影響が及ぶ重要な判断です。関連部門を含めた会議の場を設けるなどして、誰が・どの情報をもとに・どのような判断を行ったか、残課題の有無と対策について関係者間で共有しましょう。
本番稼働
切り替えが合意できたら、いよいよ新WMSを稼働させます。 リスクの少ないタイミング(日程、時間)を選択する以外にも、以下のような対策が考えられます。
- ・出荷作業を前倒しするなど、稼働開始日の処理件数を減らす
- ・トラブル発生時の連絡網、判断者を決めておく
- ・稼働開始日や1か月後に反省会を行い、現状・課題・対策について整理する
まとめ
導入の1~2カ月前から行う準備作業は、新WMS立ち上げ時のトラブルを低減するために重要です。 当コラムでは、計画編・実行編の2話にまたがり、準備の重要性とすべきポイントを解説してきました。 しかし、導入前に期待した効果が得られる一番のポイントは「ユーザー自身の主体性」にあると思います。 システムはベンダーが詳しいのですが、現場運用に一番詳しいのはユーザー企業です。 そこには長年培ってきた経験や、現場作業者しか知りえない多くの知恵が詰まっています。 WMSの導入にも是非そのノウハウを活かして欲しいと思います。 ユーザー自身が当事者意識を強く持ち、主体的にテストパターンを作成したり、入念なリハーサルを 行うことで、WMSプロジェクトが成功し、当初期待した効果を享受することができるのです。 今回ご紹介した内容は、様々な業種・業態の企業で参考にしていただけるものです。 ベースとして参考にしていただきつつ、自社の特性を加えてご活用ください。








