深刻化するトラック・ドライバー不足
国内貨物輸送量のうち、トンベースで9割、トンキロベースで5割を担うトラック輸送のドライバーが不足し、産業や暮らしに影響が出ています。個々の荷主企業や物流企業を見ると、その程度は一様ではありませんが、不足感には例外がないといった状況です。
激減する若年ドライバー
トラック輸送は、中高年のドライバーに依存しています(図表1)。大型トラックのドライバーに占める40歳以上の割合は、平成に入ってからの四半世紀で、51.1%から72.7%と急増しています。
図表1 トラック輸送ドライバーの年齢構成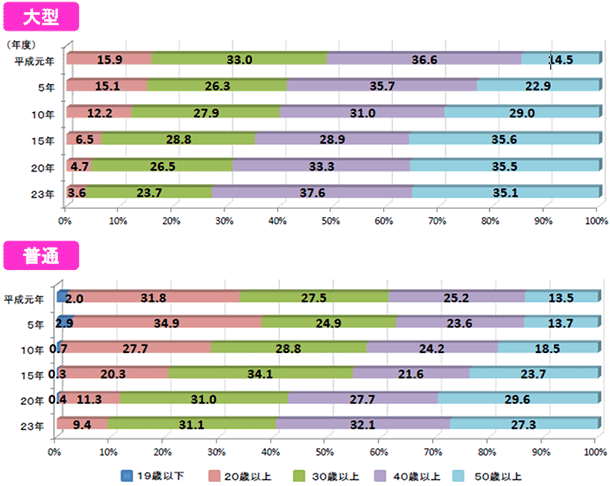
出典:公益社団法人全日本トラック協会
トラック・ドライバーが減少した理由
ドライバーの供給不足は、就職者が退職者より少ないことにあります。なぜ、以前よりも新しくドライバーになる若者が少ないのでしょうか。
運送業の職業イメージ、労働時間(休憩)、賃金、業務内容、安全・環境は、他の産業と比べてどうなっているでしょう。公益社団法人全日本トラック協会の「トラック運送事業における労働力実態調査」によれば、主に以下の違いが浮かび上がります。
- ・労働時間(長い拘束時間・連続運転時間、短い休憩時間など)
- ・賃金(月収約5万円以上の差、年収約100万円以上の差など)
- ・安全・環境(交通事故リスク、高負荷作業[手積み・手卸]、手待ち・待機など)
トラック・ドライバーの魅力度を上げる
昔は「辛いが稼げる職業」だったトラック・ドライバーのイメージは「辛いし稼げない職業」に変わり、選択肢からますます外されるようになっています。
このような現状を解決するためには、労働時間の短縮と賃金アップに取組む以外にありません。ただし、その取組みを実行するには適正な運賃の収受により、収益構造を変える必要があります。これは、荷主企業の理解なくしては不可能です。
荷主企業の理解には、トータル・サプライチェーン・コストの可視化・削減が不可欠です。その方法として、例えばサプライチェーン内で使用されるパレットのオペレーションの企業間連携・見直しなどによるアプローチが挙げられます。
物流企業は人材が確保できず、運べない。荷主企業は運んでもらえない。今回はこの状況を整理しました。次回以降は、いかにこの現状を打破するか、その方法を探ります。
トラックドライバーの賃金問題を解決する方法はこちら








