前回のコラム「3PL立ち上げの7つのポイント①」では、3つ目の立ち上げフェーズにおける「3PL立ち上げプロセスにおけるポイント」をお話しいたしました。今回でも引き続き、「立ち上げフェーズ」において、早期に確実に立ち上げるために考慮すると良いポイントについてお話しします。
関連コラム:3PLとは
目次
マニュアル整備の徹底
業務の再構築にあたって重要なのが、業務の標準化です。この標準化を現場に浸透させるために最も必要なことはマニュアルの整備です。ここでは、マニュアルに関するポイントをいくつかお話します。
作業者用のマニュアルとリーダー用のマニュアルを分けること
作業者は標準化された業務を担当することに限定し、イレギュラー発生時はリーダーへエスカレーションするように業務を構築します。よって、作業者用のマニュアルは標準業務のみの記載となります。 また、リーダー用のマニュアルは、作業者からのエスカレーションを受けた後のイレギュラー業務を詳細に記載します。イレギュラーが発生した際、作業者があたふたして対応するのではなく、リーダーにすぐに引き継いで、作業者自体はすぐに元の標準作業に戻ることにより、物流センター全体として無駄ななくスムーズな運用が構築できます。
マニュアルは荷主企業と3PL事業者と共同で作り上げること
管理者用のマニュアルも作成すること(3PL事業者のため)
作業者およびリーダー用のマニュアルだけでなく、管理者用のマニュアルを作成することをお薦めします。日次・週次・月次・年次など、どのようなタイミングで、作業の効率・品質・進捗・コストなど、どのようなポイントをチェック(評価)するなどの現場管理マニュアルです。 ここでは詳しく記載しませんが、いわゆるKPIによる現場管理手順です。物流センターの運用管理は現場管理者の腕にかかっていますので、これをドキュメントとして準備しておくと物流センターは1ランク上のレベルになります。 (KPIによる現場管理については、次回の【評価フェーズ】で詳細にお話します)
ウォークスルー(walk-through)の繰り返し
物流センター立ち上げの後半は、物流施設・設備構築とトレーニングが中心となります。大規模設備に関しては手配を漏れることは少ないですが、小規模な設備や備品などが本番当日まで手配が漏れてしまうケースがありますが、これを無くすことがウォークスルーです。 具体的には、マニュアルを手に持って、本番運用を想定して物流センター内で模擬作業を行うことで手配の漏れや運用ルールの決定漏れが必ず見つかります。 また、この模擬作業は管理者やリーダーではなく、実際の現場作業者と事務作業者にて実施します。リーダーはマニュアルを作成した本人かもしれませんし、リーダーはマニュアルに記載されていないことも想定して作業できてしまうためです。 もちろん、新物流センターで作業する全員が模擬作業を実施するのではなく、サブリーダーのポジションとなる作業者が代表で実施します。つまり、サブリーダーのトレーニングも兼ねている活動となります。 尚、ウォークスルーの際には、物流システムの環境が整っていない場合もありますが、システムが無くても、マニュアルにはシステム画面の使い方も記載されていますので、それを見ながら進めることは可能です。

現場の備品の手配漏れが無くなるまで、マニュアルに記載漏れが無くなるまで、また、サブリーダーが一通りの業務を単独で遂行できるまで、何度もウォークスルーを実施することで、本番稼働時の不安を極力減らしておくことが必要です。
無理のない計画的な引越(在庫移転)
物流センター立ち上げの最後のプロセスとして、物流センターの引越(在庫移転)についてお話します。ここまでのプロセスにて、荷主企業と3PL事業者と共同し、いかに適切な新物流センター業務を検討してきても、最後の引越が失敗してしまうと、本番稼働が延期になったり、現場で大混乱を引き起こしたりするため、無理のない計画を立てることが重要です。 既存物流センターから新物流センターへ移転する場合には、在庫の移管が伴うため、物流センターの規模によっては出荷作業を一時的に止める必要があります。 その場合、停止期間を考慮して前倒しで注文を頂いたり、少し多めに注文を頂いたりなど、納品先へ事前に連絡し調整を依頼する必要があります。また、仕入先や工場へも事前に連絡する必要もある。在庫量に余裕がある場合は、商品の搬入先を新物流センターへ切り替えるためです。少しでも引越当日の移転物量を減らすことは、作業員やトラック台数を減らして移転コストを押さえることにも寄与します。

具体的な引越作業に関しても、じっくり手順を決めておく必要があります。どのような商品から、どのようにトラックに載せていくのか、その際にどのような貼り紙を貼るのか、引越する商品の種類と数量をどのような情報で提供されるのか、などなど、決めなければならないことが山のようにあります。 また、3PL事業者が切り替わる際は、既存3PL事業者側での搬出時の棚卸、新3PL事業者側での搬入後の棚卸も必要となります。 詳細な計画・手順を定めずに、行き当たりばったりで引越すると、必ず失敗するとお考え下さい。商品の場所と数量の確定が不十分なまま時間切れで、新物流センターを稼働して、大混乱になった例をよくお聞きします。 一旦、現場が混乱すると、その立て直しには多くの時間と労力が必要となり、納品先にも多大なる影響が発生してしまいます。3PLを成功させるというテーマ以前の問題ですが、物流センター立ち上げで一番失敗しやすいポイントですので、より詳細な計画・手順の策定とその準備をおすすめします。
今回のコラムでは、荷主企業と3PL事業者と共同で、新しい物流センター業務を構築していく際に、どのようなことを考慮すると、早期に確実に立ち上げることができるかについてお伝え致しました。 次回は、3PL運用開始後、継続的に3PLの効果を享受するポイントについて、お話させて頂きます。
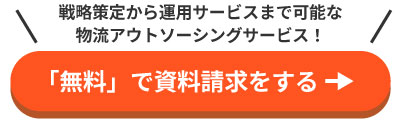
このコラムの監修者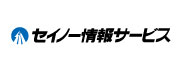 |
セイノー情報サービスは400社以上へのWMS導入を通して培った物流ノウハウをもとに、お客様の戦略立案や物流改善をご支援しています。 当コラムは、経験豊富なコンサルタントやロジスティクス経営士・物流技術管理士などの資格を持った社員が監修しています。 |
|---|








